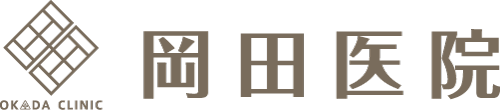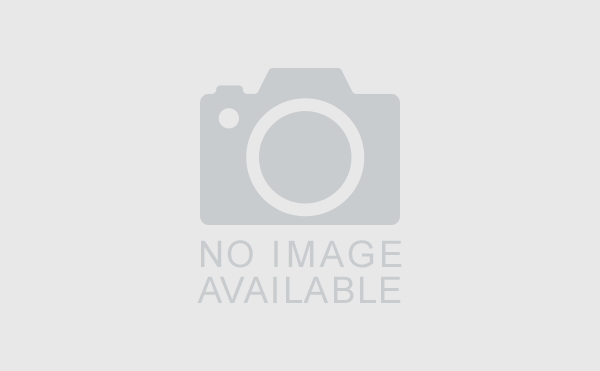動悸や息切れが続くときに考えられる循環器系の病気
「最近、動悸が続いている」「軽い運動でも息切れがしてつらい」
こうした症状が続くと、日常生活に大きな支障をきたしてしまいますよね。動悸や息切れは、普段の疲れやストレスだけでなく、循環器系の病気が関係している可能性もあります。特に高齢者や生活習慣病をお持ちの方は、心臓や血管のトラブルが原因になっていることがあります。今回は、動悸や息切れの原因となる代表的な循環器系の病気についてご紹介します。
動悸の原因
動悸とは、心拍数が速く感じたり、不規則になったりすることを言います。普段の生活で動悸を感じることはあまりないかもしれませんが、突然「胸がドキドキする」「心臓が早く鼓動しているように感じる」といった症状が現れることがあります。考えられる原因は以下の通りです:
- 不整脈
心臓のリズムが乱れることで、動悸を感じることがあります。不整脈にはさまざまな種類があり、心房細動(しんぼうさいどう)や心室性期外収縮(しんしつせいきがいしゅうしゅく)などがあります。不整脈が長期間続くと、脳梗塞や心不全を引き起こす可能性もあるため、早期の検査と治療が重要です。 - 心臓病
心臓のポンプ機能が低下することで、血液の循環がうまくいかなくなり、動悸を感じることがあります。代表的な心臓病には、冠動脈疾患(心筋梗塞や狭心症)や心不全があります。これらは、心臓への血流が十分に供給されなくなり、心臓の働きが低下することで発症します。 - 甲状腺の異常
甲状腺ホルモンの分泌が過剰になると、動悸が起きやすくなります。甲状腺機能亢進症(バセドウ病)などがその代表例です。ホルモンの過剰分泌は、体全体の代謝を速くし、心拍数が上がる原因となります。 - ストレスや不安
精神的なストレスや不安が原因で、心拍数が上がり動悸を感じることもあります。これは、交感神経が活発になるためで、急性のストレスや長期間のストレスが影響します。
息切れの原因
息切れは、普段は問題なく行えていた動作でも、息が上がってしまう症状です。息切れが長期間続く場合は、呼吸器系や循環器系の病気が関与していることがあります。以下の原因が考えられます:
- 心不全
心不全とは、心臓が十分な血液を全身に送り出せなくなった状態です。血液がうまく循環せず、体内に水分が溜まることで肺に負担がかかり、息切れが生じます。特に、安静時でも息切れを感じる場合は、心不全の可能性があるため、早急な受診が必要です。 - 肺疾患
慢性閉塞性肺疾患(COPD)や喘息などの呼吸器系の疾患でも息切れが生じます。特に、COPDは喫煙が原因で進行しやすい病気で、進行すると軽い運動でも息切れを感じることがあります。 - 貧血
貧血は、血液中の赤血球が不足している状態で、酸素を運ぶ能力が低下します。これにより、息切れや倦怠感を感じやすくなるため、鉄分の不足やビタミンB12欠乏症などが原因となります。 - 肥満
肥満は、心臓や肺に余分な負担をかけ、息切れを引き起こす原因となります。特に、肥満が進行すると、体を動かすことが難しくなり、日常的に息切れを感じることがあります。
受診のタイミング
動悸や息切れが続く場合、まずは無理せずに早期に受診することが大切です。特に以下の症状がある場合は、すぐに医師に相談しましょう:
- 動悸が突然強くなったり、不規則に感じられる
- 息切れが軽い運動や安静時でも感じる
- 胸の痛みや圧迫感を伴う
- めまいや意識がぼんやりする
これらの症状は、心臓や血管に関わる重要なサインである可能性があります。早期の診断と治療が、健康を守るためには非常に重要です。
ご案内
動悸や息切れが続く場合、放置せずに早めの受診をおすすめします。岡田医院では、循環器系の疾患に対する専門的な検査を行い、原因を明確にしたうえで最適な治療を提案いたします。
日常的に息切れや動悸を感じる方は、安心してご相談ください。心臓や血管の状態をしっかりと診断し、必要な治療や生活指導を行います。